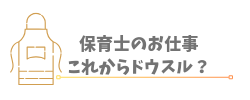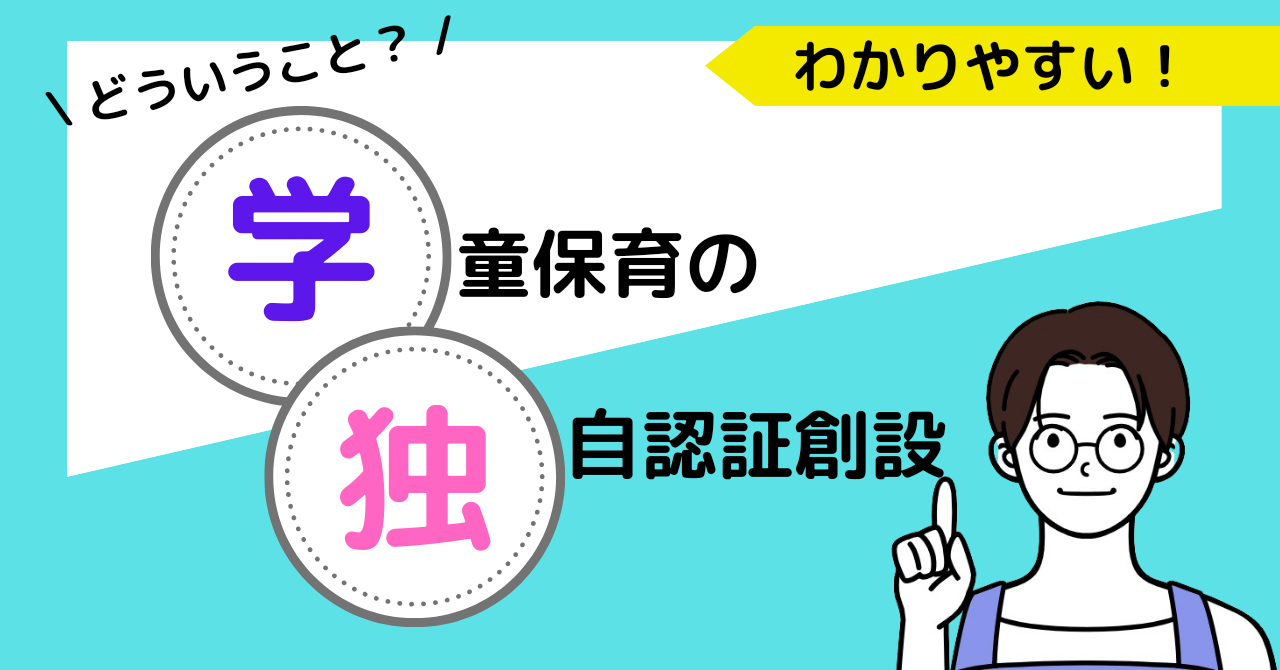東京都が学童保育の独自認証の創設というニュースをみました。どういうことなのでしょうか?

良いニュースが出てきましたね。最近は良いニュースが少ないのでうれしいです(笑)。本日は子どものステージ小学生編、保育園の後に通うであろう学童保育についてのニュースを解説したいと思います!
どんなニュース?
東京都は放課後児童クラブ(学童保育)の独自認証制度の創設に向け、専門委員会の初会合を開きました。詳しいニュースはこちら

東京都内では学童の需要が高く登録児童数は右肩上がりで増え、昨年5月時点で13万2648人となっています。そして待機児童は毎年3000人以上いる現状があります。
都内では学童の需要が高く登録児童数は右肩上がりで増え、昨年5月時点で13万2648人となっています。そして待機児童は毎年3000人以上いる現状があります。

放課後クラブと学童保育って違うんですか?

厳密にいうと若干違いがあるのですが、それも曖昧な状態なので、どちらも同じと考えていいでしょう。でも、昔は全部”学童保育”と呼ばれていましたね。以下ではまとめて”学童保育”または”学童”という表記に統一します。
※厳密にいうと放課後クラブとは児童福祉法に規定されている放課後児童健全育成事業を指します
このニュースってどういうこと?
学童保育は、国の設備運営基準がありますが、義務ではなく、地域の実情に併せて国の基準を参考にするようにとされています。(これを参酌基準といいます)

これは、どこの市に住むかによって、学童保育の環境や条件が変わってしまうという課題を秘めています。

このニュースの内容によって何が変わるんですか?

国の運営基準を上回る東京都独自の新たな運営基準を作ることによって、その基準を満たした学童保育所に「お墨付き」と与えることで、学童保育の環境・質改善を図りたい考えのようです。
この運営基準を作るための検討が始まりましたというニュースですね。

学童保育の環境や質に今までは問題があったということでしょうか?

そうですね。その問題についても、もう少し掘り下げていきましょうか。
学童保育とはどんなところ?

学童保育って行政が設置しているものではないんですか?そもそも学童保育ってどういう場所なのでしょうか?

学童保育は放課後の時間に小学生を受け入れている施設です。
主に働いている両親が放課後に預かってもらっている施設と考えていただいていいでしょう。施設は市などの自治体が設置しているものと、民間が設置しているものの両方があります。

たしかに小学校の中に設置されていたり、街なかにあったり様々ですね!

そのとおりです!小学校内はどちらかというと行政が設置していることが多いです。メリットは月額料金が安いこと、デメリットは定員が満席が多く、両親が共働きであることなど要件が厳しいことです。
街なかに多いのは民間が設置していることが多いです。メリットは入室要件がほぼないこと、習い事やスポーツ教室なども行っている場所もあること、デメリットは利用料金が比較的高いことが挙げられます。
なお、放課後クラブは児童福祉法で定められており、「授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業」と記述されています。

いつ頃から始まったんですか?私の子どもの頃もありました。
もともと学童保育は、戦前の共働き家庭やひとり親家庭の自主的な保育活動として始まったとされ、高度経済成長期で共働き家庭が増えたり、核家族化が進みいわゆる「カギっ子」が増えたことで、法律で整備されて、学童保育として始まったとされています。

そんな昔からあった事業なんですね。確かに昔は学童保育に行っている子よりも放課後は親が不在で、家のカギをぶら下がて下校するカギっ子が多かったイメージです!

そうなんです。でも今は共働き家庭が圧倒的に増えたことで、待機児童が出てしまったり、職員の人材不足など深刻な課題が出ていることも確かです。
課題とは?

深刻な課題というのをもう少し教えてください!
課題は大きく分けると4点ほどあります。
学童で働く職員の待遇が悪い
学童で働く職員の給与水準は他業種より低いことが多いです。また、離職率も高く常に職員が安定していません。

学童保育指導員の平均年収は約318万円で、離職率は15.3%となっており、日本の平均と比較すると給与は低く、離職率は高い傾向です。
不安定な運営形態
同じ場所でも、自治体によって運営形態や運営会社が変わることが多く、利用者にとって不安材料になっています。

職員が入れ替わってしまったりすると安定した関係を築くことが難しいですよね
待機児童の問題
常に定員超えのために利用できない待機児童が増加傾向にあります。そのため、待機児童により、利用は低学年の小学校3年生までと条件をつけている自治体もあります。

下記のようなニュースも報道されています。
こども家庭庁は小学生を預かる放課後児童クラブ(学童保育)に希望しても入れなかった児童が5月時点で1万8462人だったと発表した。2023年同月から2186人増加し、5年ぶりに過去最多を更新した。都市部を中心に学童保育に入れない「小1の壁」はなお深刻な状況にある。
引用:日経ニュース
学童に通いたくない児童の葛藤問題
そもそも学童は家庭(親)のニーズに合わせたもので、保育園時代とは違って、放課後帰る児童もいれば、学童へ行く児童もいる状態が生まれています。そうなると保育園時代は同じ過ごし方をしていたのが、家でゲームをやる児童、外で遊ぶ児童、学童で過ごす児童など放課後の過ごし方が違うことで、”親は学童に行ってもらいたいが、子どもは行きたくない”という事態が多く起こっています。

児童自身に学童へ通う動機づけが弱いと、友人とのトラブル・無気力・反抗的態度・脱走といった問題場面が頻発することになると言われています。
以上の4つの課題を挙げましたが、学童の利用者側も働く職員側、運営者側にもそれぞれの課題が出てきていることがわかると思います。長年運営されてきて、児童や保護者の生活を支えてきた施設だからこそ、時代が変化すれば学童のあり方も少しづつ時代に沿って変化していくことが求められるのでしょう。

このニュースは、現在の情勢に併せて、まずは過ごしやすい環境を作っていきましょうという検討をしていきますというニュースでした。
いかがだったでしょうか。
私達はいわば職員側に位置づけられます。学童で働く職員は、自身の子育てと両立した働き方、給料の低水準などまだまだ取り組んで欲しい課題は多そうですね。利用者も施設職員もお互い良い施設になって欲しいという思いは一緒のはずです。より良い方向へ向かってくれるといいですね!